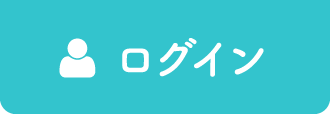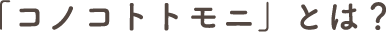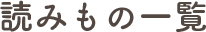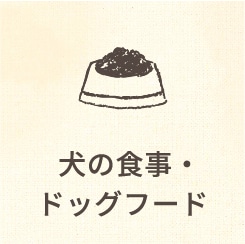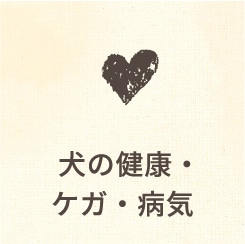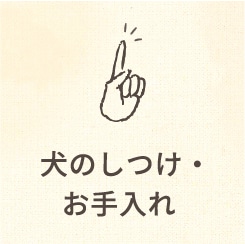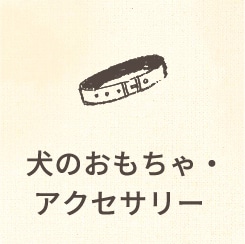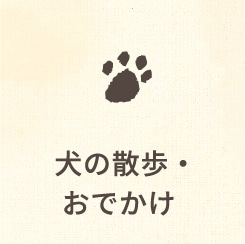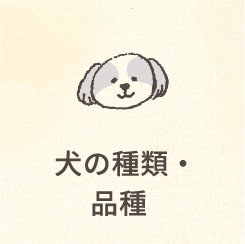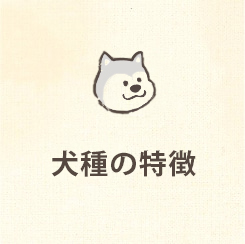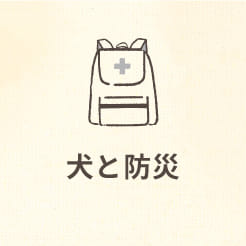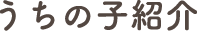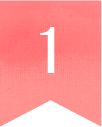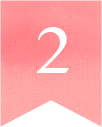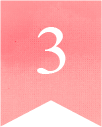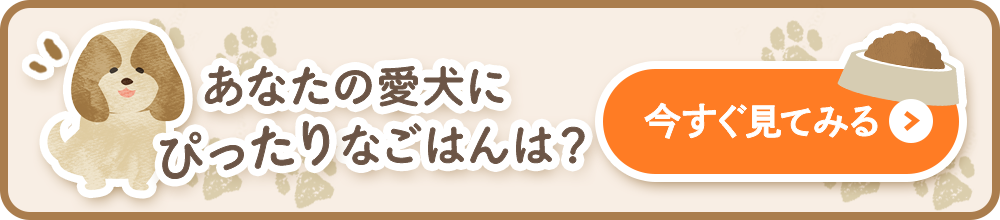犬にとってチョコレートは危険な食べ物です。
中毒を起こしてしまう可能性があるため、飼い主さんは誤って口に入れてしまわないよう十分に注意しましょう。
では、もし犬がチョコレートを口にしてしまったら、どう対処すればいいのでしょうか。
そこで今回の記事では、犬にチョコレートを与えてはいけない理由や、食べてしまった場合の適切な対応方法を解説していきます。
犬にとってチョコレートが危険な理由
私たちにとってチョコレートは美味しいお菓子ですが、犬にとっては危険な要素がたくさん含まれています。
チョコレートの主原料であるカカオの成分「テオブロミン」は、犬の体内では分解するのが難しく、蓄積して中毒症状を起こしてしまう可能性があります。
また、チョコレートに含まれている「カフェイン」も中毒の原因になりやすいです。
さらに、チョコレートに多く含まれている脂質や糖質も犬の体には良くありません。
チョコレートに限らずカカオが含まれている食品はたくさんあるため、犬に与える際は必ず原材料を確認しましょう。
少量舐めただけでも危険?
結論から言うと、「ほんの少量チョコレートを舐めたからといって即中毒が起こる」というわけではありません。
チョコレートの種類によってテオブロミンの含有量は異なること、さらには犬の体重や個体差によって中毒になったりならなかったりします。
そのため、ごく少量であれば中毒症状が出ないことも珍しくはありません。
チョコレートをごく少量舐めてしまった場合でも、1日以上様子に変化が見られなければ治療の必要はほとんどないでしょう。
犬にとって危険なチョコレートの摂取量

「犬は1㎏の体重に対して、100g程度のテオブロミンを摂取してしまうと危険」とされています。
3kg程度の小型犬の場合は板チョコレート(ミルク)1枚程度が危険量、よりカカオ成分の多いビターチョコレートの場合は、半分程度で重篤な中毒症状を引き起こしてしまいます。
テオブロミン中毒の具体的な症状としては「下痢」「嘔吐」「水をたくさん飲む」「落ち着かなくなる」などがあります。
さらには、「震え」「けいれん」「意識障害」にまで進行してしまう可能性もあります。
チョコレートを食べてから数時間後、あるいは半日程度経ってからこうした症状が出てくるので、もし愛犬がチョコレートを口にしてしまったら早めに病院に行くことをおすすめします。
愛犬がチョコレートを食べてしまったときの対処法
最後に、愛犬がチョコレートを食べてしまったときの対処法を紹介します。
万が一愛犬がチョコレートを食べてしまったら、冷静に対処するようにしましょう。
すぐに動物病院に連絡する
犬がチョコレートを食べてしまったら、自宅で様子見などはせず、一刻も早くかかりつけの動物病院に連絡をとってください。
その際は犬が食べたチョコレートの種類や量を確認し、医師に伝えることも大事です。
犬が食べたチョコレートのテオブロミン量が体重1kgあたり20mg以上の場合は、たとえ症状がなかったとしても、必ず病院に相談するようにしましょう。
ごく少量の場合も24時間は注意して様子を見る
チョコレートを摂取したのがごく少量であっても、24時間は注意して愛犬の様子を見るようにしましょう。
中毒症状は通常、食べてから数時間~半日程度の時間差で起こります。
犬によってはそれ以上の時間が経ってから中毒症状が現れることもあるため、24時間は注意して様子を見るようにしてください。
病院で行う処置

テオブロミンには解毒薬がありません。
そのため、病院では薬を使って吐かせる「催吐処置」や、時間経過してしまっている場合は「胃洗浄」などが行われます。
症状によっては、内服や点滴といった処置がプラスされることもあるでしょう。
犬がチョコレートを摂取した場合、自宅で出来る応急処置はありません。
できるだけ早く体外に排出させる必要があるので、チョコレートを食べてしまったことに気づいたら、すぐに病院に連絡してください。
犬がチョコレートを食べてしまったらすぐに病院に連絡しよう
チョコレートは人間にとって美味しいおやつですが、犬にとっては危険な食べ物です。
もし愛犬がチョコレートを食べてしまったら、すぐに病院に連絡するようにしましょう。
とくに小型犬の場合、少量のチョコレートでも重篤な症状を引き起こす可能性があります。
チョコレートの中毒症状に対して、自宅で出来る応急処置はありません。
家庭で様子見をするのではなく、早急に動物病院に連れて行くようにしてください。