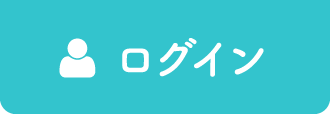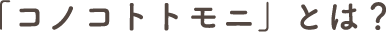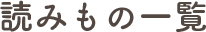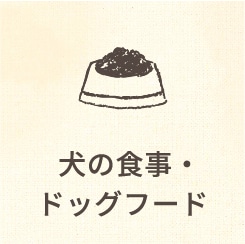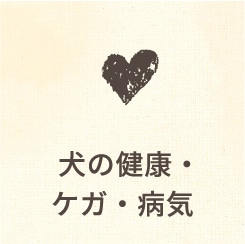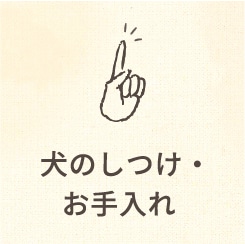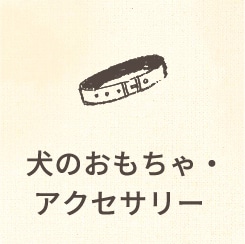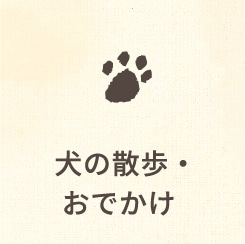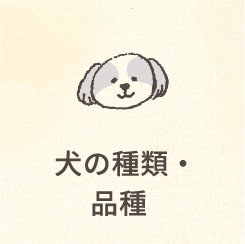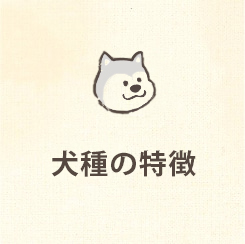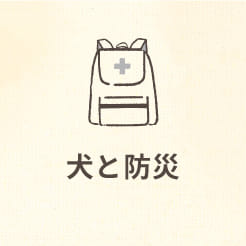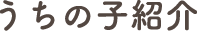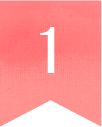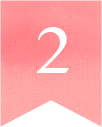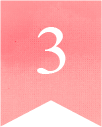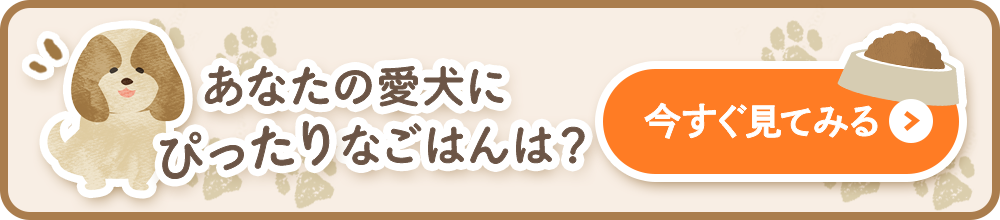愛犬にイボがあるのを見つけたら、体に影響はないのかと心配になりますよね。
犬のイボには種類があり、良性・悪性を適切に判断することが大切です。
この記事では、イボの色から良性・悪性を見分ける方法とイボができたときの対処法について紹介します。
愛犬の健康維持のため、ぜひ参考にしてください。
犬のイボは病気?良性・悪性の一般的な見分け方
犬のイボが病気かどうかは、色や硬さで判断することができます。
ここでは見た目の特徴から、イボの良性・悪性を見分ける方法について解説します。
受診前のひとつの目安として、参考にしてみてください。
ピンクの柔らかいイボは良性かも
 ※ 画像はイメージです
※ 画像はイメージです
良性イボの場合、サイズは比較的小さく1cm未満であることがほとんどです。
イボは、主にピンクや白などの明るい色味をしていて、触ると柔らかさがあります。
良性イボの多くの原因はウイルス性(乳頭腫)であり、1〜2ヶ月程度で自然に取れるのが特徴です。
カリフラワーのような見た目をしており、犬自身も痛みや違和感をあまり感じないため、気にする様子はほぼ見られないでしょう。
自然治癒後も、体に大きな影響はありません。
【良性イボの特徴】
- ピンク、黄、白など淡い色をしている
- 大きさは1cm以下で、柔らかい
- イボは大きくならない
- 数週間〜数ヶ月で自然に消失する
黒っぽい硬いイボは悪性かも
 ※ 画像はイメージです
※ 画像はイメージです
悪性イボの場合は、良性のものよりもサイズが大きく、時間とともに肥大化することが特徴です。
色味は黒っぽく、イボに触ると硬さがあります。
イボが急速に大きくなっている場合は、がんの可能性があるため注意が必要です。
悪性の特徴にひとつでも当てはまる場合は、すぐに動物病院を受診するようにしましょう。
【悪性イボの特徴】
- 赤黒、黒、紫など濃い色をしている
- 大きさが1cm以上あり、硬い
- 肥大化している
- 形状の変化が見られる
- 3ヶ月ほど経っても消えない
自己判断は難しい!病院でくわしく検査しよう
イボが良性であれば「自然に治るまで様子を見よう」と考える飼い主さんも多いかもしれません。
しかし、良性のイボだと思っていたものが実は悪性だったというケースもあります。
悪性腫瘍であれば、手術によってイボの周辺を切除することになるため、犬の負担が大きくなってしまいます。
悪化すると負担が増えるため、早期診断・早期治療が大切です。
また良性のイボであっても、化膿や炎症が起こると痛みをともなう場合もあるので、早めのケアが大切です。
「これくらいのイボで受診しても大丈夫かな?」と思わず、気になるときは病院でくわしく検査しましょう。
犬の体にイボ(できもの)ができる主な原因
犬の体にイボ(できもの)ができる原因は、主に加齢とウイルス感染の2つです。
それぞれの原因について、解説します。
加齢によるターンオーバーの遅れ
ひとつ目は、加齢にともなうターンオーバーの遅れによるものです。
皮膚が古い細胞から新しい細胞に入れ替わることをターンオーバーと言い、犬は約20〜22日(約3週間)が周期とされています。
加齢により代謝機能が衰えると、ターンオーバーの周期も遅れ、皮膚に残った古い細胞がイボを発生させてしまいます。
犬の皮膚は丈夫そうに見えますが、厚さは人間の1/3程度と薄く、外部からの刺激にとても弱いです。
健康状態が良好なワンちゃんでも、歳をとると肌のバリア機能は弱くなるため、老化現象のひとつとして理解しておきましょう。
免疫力低下によるウイルス感染
犬にイボができる2つ目の原因は、免疫力低下によるウイルス感染です。
感染源のほとんどが『パピローマウイルス(乳頭腫ウイルス)』によるもので、このウイルスは日常空間に普通に存在しています。
免疫力があればウイルスの侵入を防ぐことができますが、肌が乾燥していたり、切り傷ができていたりするとそこからウイルスが入り込み、イボの原因へとつながってしまいます。
ハピローマウイルスは生存能力が高く、犬から犬へ感染する可能性も高いです。
また、生後間もない子犬や高齢犬は免疫力が弱いため、とくにかかりやすくなります。
犬にイボができたときの対処法

愛犬にイボを見つけたら、まずは動物病院で診察を受け、原因を知るようにしましょう。
自己判断で市販薬を使用したり、放置したりするのは良くありません。
ここでは、犬にイボができたときの対処法について解説します。
受診後もイボの経過観察をする
病院を受診し、イボが良性と診断された場合でも経過観察を行うようにしましょう。
パピローマウイルスが原因であれば、イボは通常、数週間〜数ヶ月ほどで自然に消失することが多いです。
しかし、犬の健康に大きな害はなくても、イボの数が増えたり、愛犬が舐めて炎症を起こしたりすることもあるため、状態を確認しておくことをおすすめします。
イボの経過を確認するポイントは、下記のとおりです。
| 見た目 | 色、形、大きさ、数 |
| 状態 | 硬さ、皮膚への固着具合 |
| 症状 | 出血、かゆみ、化膿、破裂の有無 |
イボの様子を記録しておくことで、受診時に経過の症状を伝えやすくなります。
イボの変化に合わせて適切なケアができるように、こまめに確認しておきましょう。
頻繁にイボを触らない
顔や頭、背中などイボは全身のどの部位にもできます。
目につくため飼い主さんはイボが気になってしまうかもしれませんが、手で触れずに様子を見守るようにしましょう。
頻繁に触ると刺激によってイボが大きくなり、別の部位に飛び火する可能性もあります。
人間が神経質になると、犬もストレスを感じて舐めたり、噛んだりして症状悪化につながってしまいます。
犬にイボができてしまったら、数を増やさないことが大切です。
気になるときはシャワーやブラッシングの際に、自然な流れで状態を確認するようにしましょう。
犬のイボを見つけたら早めに受診&ケアしよう!

愛犬の体にイボを見つけたら、飼い主さんは色・大きさ・硬さなどの状態を確認し、早めに動物病院を受診しましょう。
犬のイボは、すぐに治療が必要なものと自然治癒するものがあります。
良性・悪性の特徴を紹介しましたが、見た目だけで自己判断を行うと、悪性腫瘍を見逃してしまう可能性があるため注意しましょう。
犬のイボを悪化させないポイントは、早期に気づいて予防対策を行うことです。
普段から愛犬の体をチェックし、イボができたらすぐに見つけてあげてくださいね。
まとめ
- 犬のイボはターンオーバーの遅れ、免疫力低下によるウイルス感染が主な原因である
- 良性イボはピンク色、悪性イボは黒色の可能性が高い
- イボができやすい犬種、老犬はとくに注意が必要
- 犬にイボができたときは状態を確認し、むやみに触らないようにする
- 免疫力を高める食事や身の回りを清潔に保つ生活を心がけ、犬のイボ予防をする