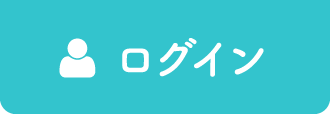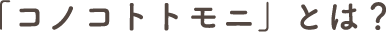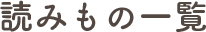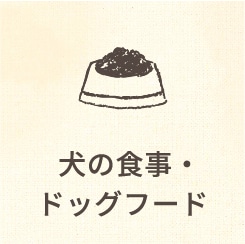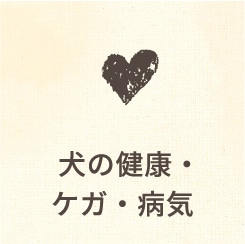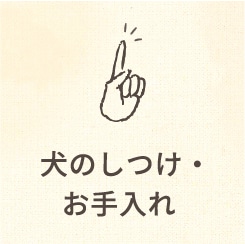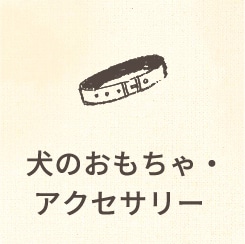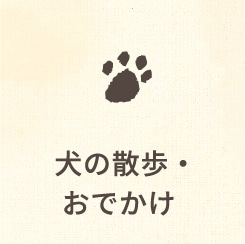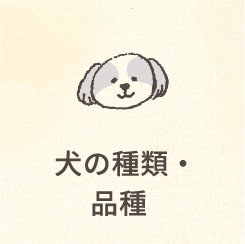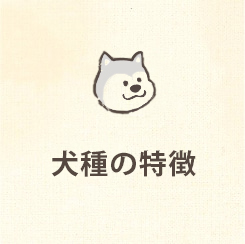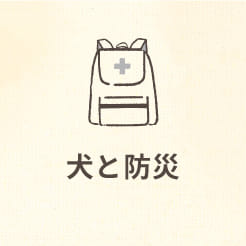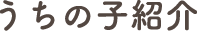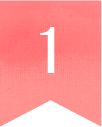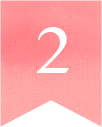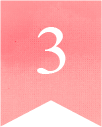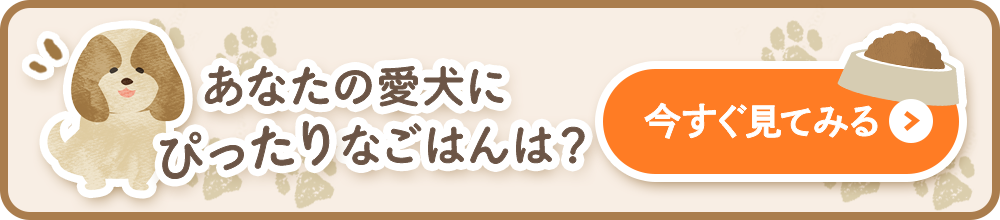ふんわりとした柔らかい毛並みや大きな目が印象的な「キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル」。
「コンフォーター(癒し)・スパニエル」という愛称を持ち、世界中の愛犬家から長く愛されている犬種です。
この記事では、キャバリアの性格や見た目などの特徴、かかりやすい病気、飼う際のポイントについて詳しく解説します。
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルってどんな犬?
「理想の家庭犬」として人気の高いキャバリアには、一体どのような特徴があるのでしょうか。
ここでは、キャバリアの性格や見た目、毛色の特徴などを解説します。
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルはどんな性格?
キャバリアは、穏やかで優しい性格をしています。
吠えたり噛んだりすることがほとんどないので、マンションやアパートなどの集合住宅でも飼いやすいでしょう。
また、非常に賢く、しつけがしやすいのも特徴です。
そのため、初めて犬を飼う人でも、小さな子供や高齢者がいる家庭でも、安心して迎えられるでしょう。
社交性や協調性があり、他の犬や猫とも同居しやすく多頭飼いにも向いています。
一方で、キャバリアには寂しがりやで甘えん坊な一面もあります。
長時間の留守番は、ストレスや不安を感じやすいので注意が必要です。
子犬の頃から留守番に慣れさせたり、留守中はお気に入りのおもちゃを置いて安心させてあげたりしましょう。
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルの見た目や大きさ
キャバリアは小型犬に分類されますが、体重は約5〜8kg、体高は30〜33cmが平均といわれていて、やや大きめです。
体高よりも体長が少し長く、胴長短足な体型をしています。
被毛はシルクのように細く柔らかで、ゆるくウェーブがかかった長毛のダブルコートが特徴です。
大きな垂れ耳と丸く大きな目が愛らしく、親しみやすい顔立ちをしています。
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルの毛色の特徴
キャバリアの毛色には、主にブレンハイム、ルビー、ブラック&タン、トライカラーの4種類があります。
それぞれの特徴は以下の通りです。
【ブレンハイム】
ブレンハイムは、ホワイトをベースに「チェスナット」と呼ばれる明るい茶色の斑点が全身に入るのが特徴です。
キャバリアを代表する毛色であり、写真映えもすることから人気が高い毛色といえるでしょう。
とくに、頭頂部に「ロザンジュ」と呼ばれるひし形や楕円形の模様があると希少性が高いといわれています。
【ルビー】
ルビーは、全身が明るい茶色のほぼ単色で、キャバリアの毛色の中ではもっとも珍しい毛色です。
白い斑点が入ることは好ましくないとされています。
【ブラック&タン】
ブラック&タンは、艶のあるブラックをベースにタン(黄褐色や赤褐色)のポイントカラーが入るのが特徴です。
タンは、目の上、頬、耳の裏側、脚の内側、尾の裏側などに現れます。
白い斑点が入ることは好ましくないとされています。
【トライカラー】
トライカラーは、ブラックとホワイトをベースに明るい茶色のタンが入る3色の毛色です。
ブラックとホワイトの境目はくっきりと分かれており、口元から胸やお腹にかけてホワイトの毛色が続く傾向があります。
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルの寿命は短い?かかりやすい病気
キャバリアの平均寿命は12.3歳とされており、小型犬全体の平均寿命14.1歳と比較すると短めな傾向があります。
これは、特定の病気にかかりやすいことが関係していると考えられています。
ここでは、キャバリアがかかりやすい病気について解説します。
僧帽弁閉鎖不全症
キャバリアは、心臓の左心房と左心室を仕切る僧帽弁が完全に閉じなくなる「僧帽弁閉鎖不全症」にかかりやすい犬種です。
この病気が進行すると、心不全や肺水腫を引き起こし命に関わることもあります。
原因ははっきりとわかっていませんが、加齢とともに発症しやすくなり、遺伝的な要因も関係していると考えられています。
乾性角結膜炎
大きな目が特徴的なキャバリアは、目の乾燥によって角膜や結膜に炎症が起こる「乾性角結膜炎(ドライアイ)」にかかることも少なくありません。
この病気を発症すると、目やにの増加や目の痛み、目のけいれんなどの症状が現れます。
原因は外傷や先天性のもの、薬剤などさまざまで、加齢によって目が乾きやすくなることも一因です。
脊髄空洞症
「脊髄空洞症」は、脊髄の中に空洞ができ、そこに溜まった液体が神経を圧迫することでさまざまな症状が起こる病気です。
この病気になってしまうと、しきりに体をかく、手足を舐める、歩行のふらつき、麻痺などの症状が現れます。
白内障
「白内障」は、眼球内の水晶体が白く濁り、進行すると視力を失う病気です。
この病気になってしまうと、物にぶつかる、歩行がぎこちなくなるなどの症状が現れます。
手術によって治療は可能ですが、症状が進みすぎると手術が困難になる場合もあります。
短頭種気道症候群
キャバリアは鼻が短い短頭種のため、気道が狭くなって呼吸がしづらくなる「短頭種気道症候群」にもかかりやすい傾向があります。
先天性の病気で、発症するといびきや睡眠時無呼吸、息切れなどの症状が現れます。
また、熱中症のリスクも高まり、進行すると呼吸困難や失神を引き起こし命に関わることもあります。
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルを飼うときのポイント
キャバリアは飼いやすい犬種ですが、健康で長生きさせるためには日々のケアが何よりも大切です。
ここでは、キャバリアを飼うときのポイントを解説します。
定期的な健康診断を欠かさない
キャバリアは僧帽弁閉鎖不全症をはじめとする、さまざまな病気にかかりやすい犬種です。
先天性や遺伝的な要因、加齢などが原因で病気になることが多く、根本的な予防が難しい場合もあります。
そのため、日頃の健康チェックと合わせて、定期的な健康診断が欠かせません。
かかりつけの動物病院でこまめに診てもらい、病気の早期発見・早期治療に努めましょう。
飼い主主導で運動量を確保してあげる
キャバリアは活発に動き回るタイプではないので、飼い主さんが意識的に運動量を確保してあげることが大切になります。
運動量は1日2回、各20分程度の散歩が目安です。
しかし、それぞれ個体差があるので、年齢や体調なども考慮して調整してあげてください。
散歩の他にも、室内の遊びを積極的に取り入れて運動習慣を作っていきましょう。
食事の管理をきちんとする
キャバリアを飼うときは、食事の管理をきちんと行い、適正体重を維持することも重要なポイントです。
肥満は、心臓病や短頭種気道症候群をはじめ、さまざまな病気や怪我のリスクを高めてしまいます。
キャバリアは食欲旺盛で甘え上手なので、フードやおやつを与えすぎないように注意しましょう。
主食には、必要な栄養素がバランスよく含まれている総合栄養食を与えることをおすすめします。
年齢や健康状態などに合った、愛犬に合うペットフードを選んであげましょう。
室温管理や体温調節に気をつける
キャバリアは保温性の高いダブルコートで、比較的寒さに強い犬種です。
しかし、暑さには弱いので、エアコンや冷感アイテムなどを活用して、室温管理や体温調節に気をつけてあげましょう。
エアコンの設定温度は、夏は25度、冬は22度が目安です。
また、真夏や真冬の散歩では、急激な寒暖差によって免疫力の低下や熱中症を起こす恐れがあるので注意しましょう。
換毛期のブラッシングは丁寧に行う
キャバリアは基本的にトリミングは必要ありません。
しかし、抜け毛を取り除くために日頃からきちんとブラッシングを行いましょう。
耳の裏や脇の下、内股は毛玉ができやすいので、念入りにブラッシングしてください。
とくに、換毛期は抜け毛が多くなります。
抜け毛を取り除くことは暑さ対策にもなります。
1日1回はブラッシングを行うのが理想的だといえるでしょう。
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルの歴史

キャバリアはイギリス原産の犬種で、その祖先は16世紀頃の鳥猟犬「スパニエル種」と考えられています。
19世紀になると、スパニエル種とアジア系の短頭種が交配され、キャバリアよりもひと回り小さく鼻先の短い「キング・チャールズ・スパニエル」が誕生しました。
この犬種はイギリスをはじめ、ヨーロッパの王室や貴族たちにも大変愛されたといわれています。
しかし、その後いびきのうるささや呼吸疾患にかかりやすいことが欠点だとされ、本来のスパニエル種らしさを取り戻すために「戻し交配」が行われるようになりました。
その結果、中世の騎士を意味する「キャバリア」を冠した現在の犬種が誕生したといわれているのです。
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルは優しくて飼いやすい
キャバリアは愛らしい見た目や優しい性格で、多くの人を魅了します。
賢くコミュニケーション力も高いので、初めて犬を飼う人や他にペットがいる家庭でも迎えやすい傾向があります。
しかし、キャバリアはさまざまな病気にかかるリスクが比較的高めです。
そのため、適切な健康管理や環境を整えてあげる必要があります。
キャバリアを飼う際には、健康に気を配り、日々のケアを丁寧に行ってあげましょう。