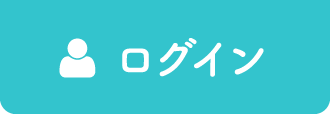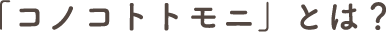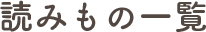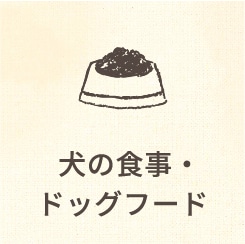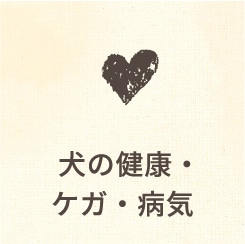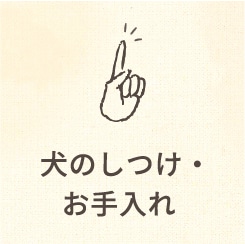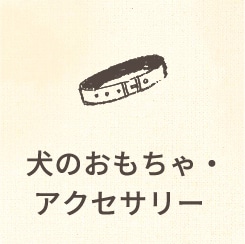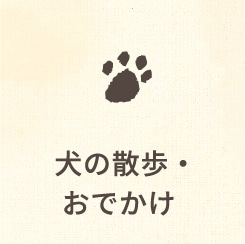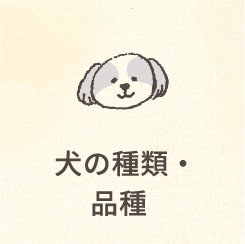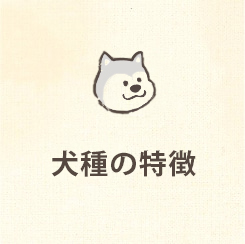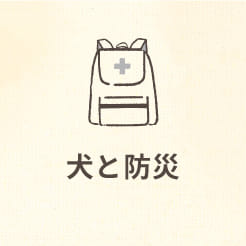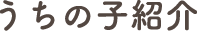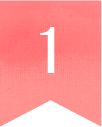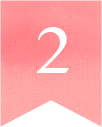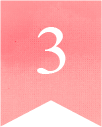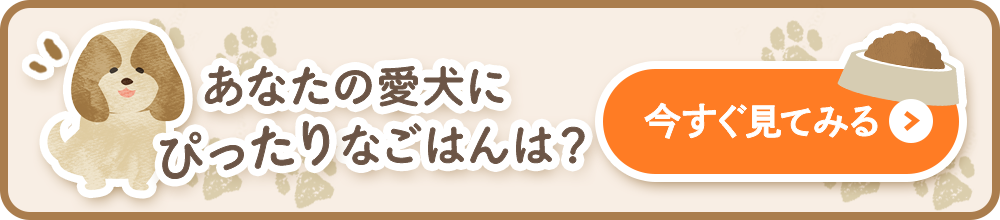甘くて美味しいとうもろこしを愛犬にも与えたいと思う飼い主さんは少なくないでしょう。
愛犬にとうもろこしを与えるのは問題ありませんが、「生で与えてはいけない」「芯が誤飲の原因になる」など与えるときにはいくつか注意点があります。
この記事ではとうもろこしを与える際の注意点などを紹介します。
愛犬にとうもろこしを与えても大丈夫?
結論から言うと、犬にとうもろこしを与えても問題ありません。
とうもろこしにはビタミンB1や葉酸、ナイアシンなどの栄養素が含まれているため、愛犬の健康維持にも役立ちます。
ただし、生で与えてしまうと消化不良の原因になる可能性があるので、茹でた身をすりつぶして与えるようにしましょう。
とうもろこしに含まれる栄養
【 糖質 】
糖質は身体に必要なエネルギー源です。
摂取後、消化・吸収され血液とともに身体中をめぐってエネルギーに変わります。
同じエネルギー源であるタンパク質や脂質と比べて、消化・吸収が早い特徴があります。
また、脳は血液中の糖質をエネルギー源としているので、糖質が不足すると意識障害が起こることがあります。
糖質は脳を正常に動かすためにも必要な栄養素といえます。
【 葉酸 】
とうもろこしにはさまざまな栄養が含まれていますが、中でも葉酸が多く含まれています。
葉酸は成長やDNAの形成をサポートする大事な役割がある栄養素で、細胞の分裂や成長にも大きく関わっています。
葉酸は人間でも妊娠中の人が積極的に摂るといい栄養素ですが、犬の場合も同じなので妊娠している子には与えたい栄養素のひとつです。
【 カリウム 】
とうもろこしにはカリウムが豊富に含まれています。
カリウムは細胞内液に存在し、細胞と細胞の間の水分に存在するナトリウムとうまくバランスをとって、体内の状態を正常に維持するために役立っています。
その働きは血圧の調整、代謝活動などです。
カリウムが足りなくなると神経過敏や不整脈などの症状が出る場合があります。
【 食物繊維 】
とうもろこしの身には食物繊維のセルロースが豊富に含まれています。
セルロースには腸内をきれいにして便秘を予防してくれる働きがあるので、便秘がちの犬に与えると便秘改善が期待できます。
また、食物繊維には腸に糖が吸収される速度を遅らせる働きがあります。
食事をした時には血糖値が上昇しますが、これが急激に上昇すると糖尿病の原因になります。
食物繊維を摂取することで、血糖値が急激に上昇するのを予防してくれるのです。
犬でも糖尿病になることがあるので、予防が必要になります。
また、食物繊維にはコレステロールを下げる働きがあるので、コレステロールが気になる犬にはおすすめの栄養素です。
【 ナイアシン 】
ナイアシンはビタミンB群のひとつで、脂質や糖質をエネルギーに変換するときに働く酵素をサポートする補酵素として働きます。
また、粘膜や皮膚の健康を維持して脳神経を正常にする役割を持っています。
ナイアシンは水溶性のビタミンですが、熱湯に溶け出す性質があるので、とうもろこしを茹でたお湯を使ってスープにするといいでしょう。
犬におもちゃとしてとうもろこしの芯を与えてもいいの?

とうもろこし自体は食べても問題ないため、硬く噛みごたえがあり、犬が好みそうな芯をおもちゃとして与えようと考える人もいるのではないでしょうか。
しかし、芯を誤飲してしまうと消化不良や腸閉塞を起こしてしまう危険があるため、おもちゃにするのは絶対にNGです。
どのような危険があるのか、詳しく解説します。
とうもろこしの芯は誤飲してしまうことがあるので与えないで!
とうもろこしの芯は、犬の誤飲の原因として上位に入っています。
もしおもちゃとして与えている場合は、すぐにやめてください。
とうもろこしの芯は硬く、食物繊維の塊です。
犬は人間よりも食物繊維の消化や吸収が苦手なので、とうもろこしの芯を飲み込んでしまうと胃の中でとどまったり、腸に詰まったりする可能性があります。
食道に引っかかってしまうと呼吸困難を引き起こす恐れもあり、大変危険です。
誤飲を防ぐためにも、とうもろこしの芯を与えないで、実の部分だけをあげるようにしましょう。
とうもろこしの芯を誤飲すると嘔吐や下痢の原因になる
犬がとうもろこしの芯を飲み込んでしまうと、芯が腸に詰まって腸閉塞になることがあります。
そうなると、嘔吐や下痢、腹部膨張、便秘、意識障害などのさまざまな症状が表れます。
腸閉塞の嘔吐の特徴としては、食後に何度も嘔吐し、吐き終わったらケロッとして元気になることが挙げられます。
腸閉塞を引き起こすと開腹手術が必要になり、最悪の場合は命を落とすこともあるため、芯は絶対に与えないようにしましょう。
犬がとうもろこしの芯を食べたときの対処法
犬がとうもろこしの芯を飲み込んでしまったら、すぐに病院へ連れて行きましょう。
早く行けば、とうもろこしの芯が腸に行く前に嘔吐させることができます。
嘔吐や下痢の症状が出てからでは愛犬が苦しむだけなので、見つけたらすぐに連れて行ってあげましょう。
犬にとうもろこしを与えるときの注意点
とうもろこしには犬の健康維持に役立つ栄養素が多く含まれているため、積極的に与えたいと思う人もいるでしょう。
もちろん与えても問題はありませんが、与える際には注意点があります。
とうもろこしを与える場合の適量や注意点を解説しますので、しっかりと理解しておきましょう。
とうもろこしアレルギーに注意
犬の体質によってはとうもろこしがアレルギーの原因になることがあります。
アレルギーの症状としては、身体のかゆみや嘔吐、下痢、蕁麻疹、目の充血などが挙げられます。
初めてとうもろこしをあげるときは少しずつ与え、体調に異変がないかしっかりと観察しましょう。
与えるとうもろこしの量に注意
とうもろこしには不溶性食物繊維であるセルロースが豊富に含まれているので、大量に摂取すると消化できず、消化不良を起こしてしまいます。
そうなると消化器官に負担をかけて、嘔吐したり下痢を引き起こしたりする原因になります。
また、とうもろこしにはカリウムが含まれているので、おしっこが普段より多くなることもあります。
犬にとうもろこしを与える場合は、1日に10~15g程度が適量です。
普段のフードを含む1日の総摂取量に対して、10%以内にとどめるようにしましょう。
とうもろこしを生で与えるのは避ける
犬にとうもろこしを食べさせるときは、生のままだと噛まずに飲み込んでしまうため、栄養の吸収ができないだけでなく、消化不良を起こす恐れがあります。
とうもろこしを犬に食べさせるときは、必ず茹でて実をすりつぶしてからあげるようにしましょう。
また、塩茹ですると余分な塩分を摂取させてしまうので、塩は入れないようにしましょう。
犬にとうもろこしを与えるときは適量を守ろう

とうもろこしには豊富な栄養が含まれているので、愛犬の健康維持に役立つ食材です。
しかし、「与えすぎると消化不良の原因になる」「芯を誤飲してしまう可能性がある」など与える際にはいくつか注意点があります。
とうもろこしはあくまでおやつなので、適量を守って主食に影響しない範囲で愛犬に与えるようにしましょう。