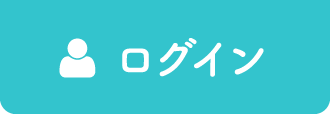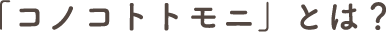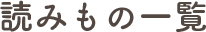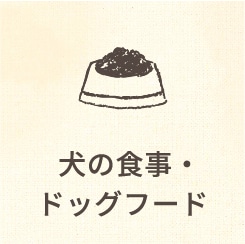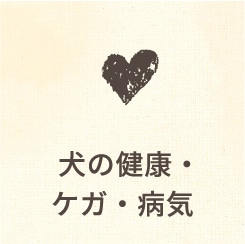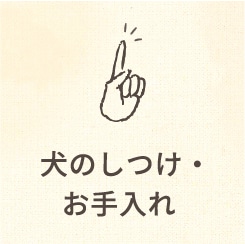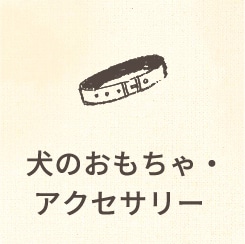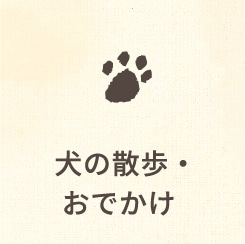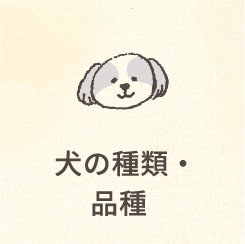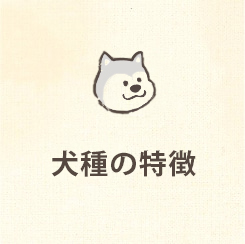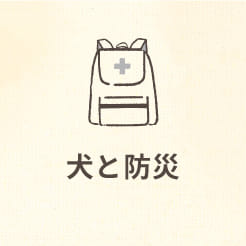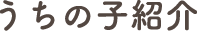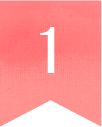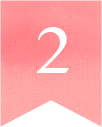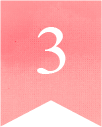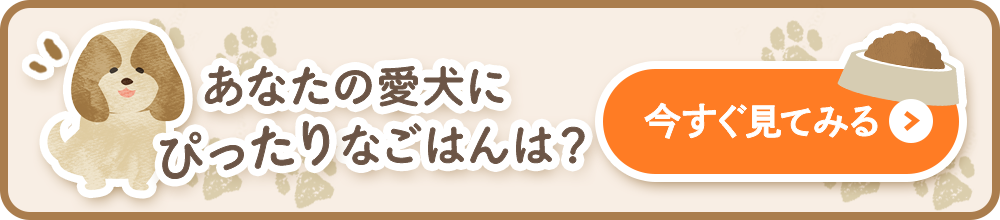鶏ささみはタンパク質が多く、栄養価の高い食べ物です。
低カロリーで良質なタンパク質が摂取できるので、人間のダイエットや美容にも役立つことで知られています。
では、ささみは犬にとっても有益な食べ物なのでしょうか。
そこで今回の記事では、犬にささみを与えるメリットや、与える場合の注意点について詳しく解説していきます。
犬にささみを与えても大丈夫!ただし生はNG
ささみは犬に与えても問題のない食べ物です。
雑食の犬にとっては消化しやすく、安全性の高い食べ物の一つだといえるでしょう。
また、低カロリーでありながら良質なタンパク質をたくさん含んでいるので、犬が食べるメリットも多いです。
ただし、鶏肉にはカンピロバクターをはじめとした細菌が付着していることがあるので、生で食べさせるのは絶対NGです。
食中毒を引き起こさないためにも、ささみは必ず加熱して与える必要があります。
犬にささみを与える際の1日の適量
ささみを食べさせる場合は、わんちゃんの体格に合わせた量を与えてあげましょう。
基本的に、ささみはおやつ扱いでありメインで与えるのはNGです。
あくまでも食事の補助、おやつとして活用することを前提として考えてください。
おやつの一般的な適量は、普段の食事カロリーの10%以内とされています。
これ以上与えてしまうと、本来食べるべき食事量に影響して、栄養バランスを崩してしまう可能性があるので、与えすぎにはくれぐれも注意しましょう。
ここでは、体重別にささみの1日当たりのおおよその適量を紹介します。
どのくらいまで与えていいのか迷ったときは、ぜひ参考にしてみてください。
| 犬の体重 | 1日のささみ給与量 |
| 体重5kg未満 (超小型犬) |
1.5本程度まで |
| 体重5kg~10kg未満 (小型犬) |
2.5本程度まで |
| 体重10kg~20㎏未満 (中型犬) |
3.5本程度まで |
| 体重20㎏以上 (大型犬) |
5.5本程度まで |
犬にささみを与えるメリット4選

続いて、犬にささみを与える具体的なメリットを見ていきましょう。
良質なタンパク質が豊富に含まれている
ささみには良質なタンパク質が豊富に含まれています。
タンパク質は、活発に動く犬にとって欠かせない栄養素です。
筋肉の発達や維持、被毛の美しさ、歯や骨の健康にも大いに役立ちます。
また、犬は必要なタンパク質の比率が人間よりも多いので、ささみはわんちゃんの健康維持のために非常に重要な役割を持っているといえるでしょう。
低カロリー・低脂質で肥満防止になる
肉類は犬にとって欠かせない食べ物ですが、食べ過ぎるとカロリーが心配です。
しかし、ささみは低カロリー・低脂肪なので、そこまで太り過ぎを気にせず与えることができます。
さらに、鶏ささみには脂質や糖質の代謝を活発にする「ナイアシン」が含まれています。
そのため、食べることでダイエット効果も期待できるでしょう。
アミノ酸やビタミンの働きで疲労回復できる
ささみには、アミノ酸やビタミンB群が豊富に含まれています。
これらの栄養素には、筋肉の疲れやエネルギー代謝を高める効果があるので、たくさん摂取することで疲労の回復が期待できます。
とくに、活発な犬やドッグランなどでたくさん遊んだ後の犬には、疲労回復も兼ねてささみをおやつに与えてあげるといいでしょう。
抗酸化作用のあるセレンが含まれている
ささみには、抗酸化作用のある「セレン」というミネラルが含まれています。
抗酸化作用とは、老化や生活習慣病の原因となる活性酸素による酸化を抑えてくれる働きのことです。
抗酸化作用のある栄養素を摂ることで、健康維持やアンチエイジング効果が期待できます。
セレンを含んだささみを定期的に食べさせることで、わんちゃんの体を健全に維持し、若さを保つことができるでしょう。
犬にささみを与えるときの4つの注意点
いくらささみが体に良いとはいえ、やみくもに犬に与えてはいけません。
ここでは、犬にささみを与えるときの4つの注意点を解説します。
絶対に生で与えないようにする
犬にささみを食べさせるなら、絶対に生で与えてはいけません。
生の鶏肉にはカンピロバクターなど、多くの危険な細菌が付着しています。
そのため、生で食べさせてしまうと食中毒を引き起こし、最悪の結果を招く可能性があります。
カンピロバクターを死滅させるためには、65度以上の熱で数分間加熱しなければいけません。
愛犬の健康を守るためにも、必ずささみには火を通してください。
毎日ペットフードにトッピングしない
ささみを積極的に食べさせたいからといって、毎日ペットフードにトッピングするのはおすすめできません。
ささみを毎回ペットフードにトッピングしていると、栄養バランスが崩れて大切なカルシウムの吸収を阻害してしまう恐れがあるのです。
カルシウムを適切に摂取するためには、「リン」とのバランスが重要だとされています。
理想的な比率は「カルシウム:リン=1:1〜2:1」とされており、このバランスが崩れるとカルシウムの吸収率が低下してしまいます。
ささみにはリンがたくさん含まれています。
そのため、毎食摂取してしまうとリンの過剰摂取になり、カルシウムが十分に吸収できなくなってしまうのです。
栄養バランスが整えられたペットフードのバランスを崩してしまわないためにも、過剰にささみを与えるのは避けた方がいいでしょう。
塩や香辛料で味付けしない
ささみが淡泊な食べ物だからといって、塩や香辛料で味付けするのはNGです。
犬にとって塩や香辛料は、病気のリスクを上げる要因になってしまいます。
とくに香辛料には、犬が摂取できない玉ねぎやナツメグなどが含まれている可能性があるので大変危険です。
味付けせずに加熱して、そのまま食べさせてあげてください。
鶏肉アレルギーに気をつける
どんな食品でもアレルギーのリスクがあります。
ささみを与える場合も、わんちゃんのアレルギーには十分気をつけるようにしましょう。
初めて与える際は少量にし、アレルギーが出ていないかしっかりと確認してから徐々に量を増やすようにしてください。
万が一、鶏肉摂取後にかゆみ、目や肌の赤み、下痢、嘔吐といった症状が見られたら、すみやかに動物病院で受診するようにしましょう。
愛犬のために!ささみのおすすめの与え方

最後に、おすすめのささみの与え方を紹介します。
わんちゃんの体格や年齢、食欲に合わせて適切に食べさせてあげてくださいね。
茹でるかレンジで加熱する
犬に与えるささみは、スーパーなどで売っている一般的なものでOKです。
ただし、食中毒を防ぐためにも、火をしっかり通して与える必要があります。
そこでおすすめなのが、茹でるかレンジで加熱する方法です。
茹でる場合は、沸かしたお湯にささみを入れて弱火で10分程度加熱しましょう。
レンジを使用する場合は、耐熱容器に入れてラップをし600Wで2分間加熱、その後余熱で火を通してあげます。
どちらの方法にせよ、加熱後にカットして中までしっかり火が通っているか目視でも確認することが大事です。
子犬やシニア犬にはペースト状にしてあげる
子犬やシニア犬にとって、ささみは少々噛み切りづらい食べ物です。
噛む力の弱いわんちゃんに与えるときは、火を通したささみをミキサーにかけて、ペースト状にしたものを与えるようにしましょう。
ペースト状にすれば消化しやすくなるので、消化力の弱い子犬やシニア犬にも安心です。
ささみの茹で汁やスープを与えるのもおすすめ
ささみそのものではなく、ささみの茹で汁やスープを与えるのもおすすめです。
食欲がないわんちゃんには、フードにささみの茹で汁をかけ、食いつきがよくなるように工夫してあげましょう。
また、カロリー制限の必要なわんちゃんには、茹で汁やスープで鶏の風味だけを楽しんでもらうという方法もあります。
鶏ささみは肉そのものだけでなく、スープなどさまざまな形で活用できるので、愛犬の体調や食欲に合わせて与えてあげてください。
犬にささみを与えるときはきちんと加熱しよう
ささみは人間だけでなく、犬にとってもメリットの多い食べ物です。
栄養価が高く、手軽に良質なたんぱく質やビタミンが摂取できるので、犬の健康維持のために食事に取り入れましょう。
ただし、犬に与える際は、必ずしっかり火を通してからにしてください。
また、摂取しすぎるとかえって栄養バランスを崩し、リンの過剰摂取になる恐れもあるので、食べさせすぎにも注意が必要です。
ささみのメリットや注意点をしっかりと踏まえた上で、ぜひわんちゃんのおやつとして活用してみてくださいね。